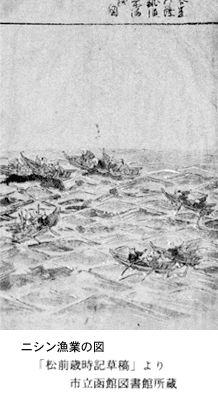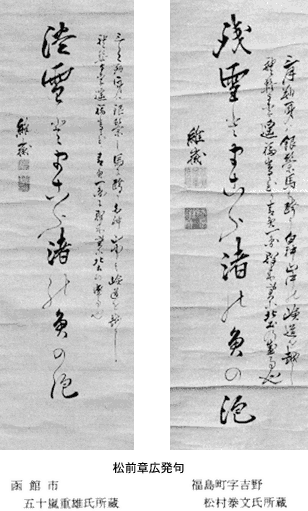第一節 漁業の変遷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ニシン漁業】 近世蝦夷地の漁業の中核をなしたものはニシン漁業である。ニシンは和名を「かど」、「青魚」「鯖」「白」「鰊」の文字をあてていたが、近世において特に「鯡 」の俗字が用いられていた。蝦夷地では米が穫れず、ニシンが肥料として本州へ移出され、米となって還元されて来るので、米に代わる魚として「鯡 」という字が造られたといわれている。それほど、ニシンは蝦夷地の漁民にとって重要な魚であったが、また、海流の関係かこれ程豊凶の激しい魚はなかった。 このニシンは春二月末(旧暦)津軽海峡東口に姿を見せ、順次海峡部、福山湾を経て北上の過程で、群をなして海岸に迫って産卵するので、沿岸は白く泡立ち、これを「群来(くき)る」と言った。三月から四月を最盛期とし、五月には終るが、五、六月は製品の処理に追われ、六月末に完了する。 ニシン漁業は近世のやや末期まで刺網が用いられたが、その網について『夷諺俗話(いげんぞくわ)』では
とあって、ニシン漁業は網一把(一反)×五把で一放(約四一メ-トル)をおよそ四~五放を磯舟又は保津船で従業漁夫三、四人で一か統を経営したが、資力のあるものは図合船を用いて十放から二十放位 まで経営する者もあった。 漁業技術が向上し宝永年間(一七〇四~一〇)ころから漁網が改正され大網が使用されるようになった。これは場所請負人が請負場所に大形投資をして、漁獲量 を高めるための手段であったが、そのためには多くの資金と資材、漁夫を必要とし、津軽、下北、秋田から多くの入稼漁夫が入るようになった。しかし、和人地の漁民は資金も乏しく、幕末まで依然としてこの刺網漁を続けていた。この大網でニシンを獲る漁業が発達すると、一度に大量 のニシンを水揚げするので、ニシン加工の処理ができず、これを釜で煮て干し、魚油を製造するほか、煮魚を干して粕とし、本州農家の畑作肥料として移出するようになった。 ニシン漁業は豊凶を繰り返す不安定な漁業で、奥地各場所で大網を用いるようになると、その豊凶は激しくなった。明和年間(一七六四~七一)はこの漁の最も安定した時代といわれるが、安永五~六年(一七七六~七七)道南地方で薄漁となり、天明二年(一七八二)以降は桧山地方が薄漁となり、同年以降はますますはなはだしく、生活に苦しんだ漁民は追ニシンをして西蝦夷地に出漁し、その地方のニシン漁は大いに進展するようになった。この追ニシン漁者のことを二・八取(にはちとり)とも呼ばれるが、それは場所請負人に二割を納めることによるものである。このようなニシンの薄漁は、場所請負人が各場所で大網(角網、笊(ざる)網)で一挙に大量 のニシンを取り、これを搾油するからだと、寛政元年(一七八九)江差地方の漁民はその禁止を求めて藩に願い出たが、藩は何らの措置を講じなかったので、翌二年には漁民は積丹半島付近まで大網切断の実力行使をするなど紛争は絶えなかった。藩はそのため追ニシンの石狩までの進出を認めたため、道南地方の漁業者が二・八取としてこの地方に出稼する者も増加した。 収獲されたニシンは和人地、西蝦夷地の季節稼働者が多くなると、さまざまに加工され本州各地に移出された。領主松前氏の幕府献上品のなかにニシン加工品に鰊披、鰊干物(身欠鰊)、鰊子(数の子)、寄鰊子(寄せ数の子)があるが、そのほかには粒鰊、筒鰊、早割(さきり)鰊、外割(ほかわり)鰊、胴鰊、白子、笹目、締粕、鰊油等がある。粒鰊は生のニシンの事をいい、筒ニシンは一本干をしたもの、早割、外割は背割をしたニシンを披いて干したもので、披(ひらき)ニシンともいう。胴ニシンは身欠ニシンを取った後に干したもので主に肥料となる。白子、笹目はニシンの加工の内臓やエラを干したものでこれも肥料となる。数の子はニシンの腹子を干したもの。締粕はニシンを大釜で煮て締機で圧縮し、玉 にし、それを天日で乾燥させたもの、ニシン油は締粕を造る際、分離した油である。 ニシンは近世初期には生の食料にするか、天日で一本干をする筒ニシンあるいは身欠ニシンにするより方途がなかったが、中期以降に入ると、九州国東(くにさき)半島付近で生産され、全国の農業作物の肥料として需要の多かった干鰯ほしかが渇し、関東九十九里浜の生産も低下したことから、近江商人が、身欠ニシンを取った後の廃棄同様の胴ニシン、白子、笹目等を北国、関西地方の田畑で試用の結果 、干鰯に遜色のないことが分かり、大々的に喧伝した結果その需要が大幅に拡大した。この時期は享保年間(一七一六~三五)以降といわれるが、それに従い西蝦夷地の大網使用による大量 水揚げ、入稼漁夫の拡大によって加工品の増産等、本州需要の増加に対する対応が見られ、ニシン漁業はますます拡大された。 【福島のニシン漁業】 福島町のニシン漁業のはじまりは、昭和十年に刊行された『北海道漁業志稿』(北水協会編纂(へんさん))の冒頭に、「文安四年(凡四百四十餘年前)陸奥の民馬之助と稱する者、松前地方(今の白符村付近)に来り、鰊漁に従事す」と記されていて、これが根拠となって福島町がニシン漁業発祥の地であるといわれている。しかし、この漁業志稿が何を出典としてこの記事を書いたかは不明であって、極めて出典根拠に乏しいものである。 馬之介の白符村入植の過程については、『白符・宮歌両村舊記』(北海道大学附属図書館蔵)があり、元文四年(一七三九)白符村と宮歌村との村堺問題で訴訟となったとき、開村の経過を記した文献があり、それによると、
とあって、津軽ねっこ村(現在の南津軽郡田舎館村)から馬之介というものが蝦夷地に入って来て、白符村に居住し、村の代表者となったことは確かであるが、前記史料から見ると、馬之介の白符定着の年代は文安四年(一四四七)より一五〇年の後の寛永年間以降の事と推定される。それは殿様の命により肝入となったといっており、各村役の任命はこの寛永年間以降の事であるので、馬之介が白符村に定着し、ニシン取をしたというのは、それ以後の事であると考えられる。しかし、このような口碑伝説のあることを大切にしなければならないが、福島町のニシン漁業は各村に我々の先祖が定着した時から始められていることは確かである。
福島町内の各村にニシンが廻游するのは、旧暦の二月中旬から三月にかけてである。ニシンは津軽海峡東口から海峡中央部を通 り、矢越岬から陸岸沿に松浦の楚湖岬にぶつかり、方向を変え、礼髭沖から吉岡海岸、日方泊を経て月崎、釜谷を経て大きく迂廻し、沖合に出て白神岬を越えて、松前沖を経て北上するというコ-スを取っていた。従って下海岸、上磯、木古内、知内等は遙か沖合を通 るためあまり漁獲がなく、本格的にニシン漁の始まるのは福島沖であったので、福島沖がその年の水揚げの吉凶を占う場所として極めて重要な場所であった。従って松前領内でニシンの初水揚げされるのは福島湾内であるので、水揚げをした場合直様(すぐさま)名主の処に届けられ、名主はそのニシンを魚献上箱に入れて小役の者に持たせて、吉岡峠を登って城中に届けると、藩主以下重臣が列席して祝詞を述べることが慣例となっていた。また、ニシンの廻游経路については、『常磐井家文書』の日記に詳しく、次のように記してある。
とあって、ニシンの初水揚は、凡そ二月中旬から三月中旬で、その廻游経路も前述のとおりであるが、ニシンの群来るときは正に漁師の生命を賭した戦の場で、僅か三十~四十日間で一年の生計を生み出すため、総てをこの期に集中していた。 年中行事のなかの歳時記を見ると、村の一年はニシン漁業を中心とした生活であったが、月別 にそれを見ると、
この福島町のニシン漁業を中心とした一年の年中行事は、町史編集過程で知り得た漁業者の生活をまとめ上げたものである。 このような年中行事の過ごし方もニシン漁業の豊凶によって、年によって極端な生活の変化があった。豊漁の場合はニシン漁のみで、一年の生活をするだけの収入があり、凶漁の場合は全く収入がなく、磯廻り漁業や鮑(あわび)、海鼠(なまこ)、若布(芽)採、昆布採、鰯(いわし)漁業等でようやく糊口をしのぐという状況であった。福島町内で往時ニシンがどの位 獲れたかを示す史料はないが、天明二年(一七八二)蝦夷地に渡り見聞した平秩(へつつ)東作の著した『東遊記』のなかで、そのニシン漁業収入のことを次の如くに記している。
といっており、不漁年のこの年でも、全く素人の医者が三人組んで、刺網をし、一人当り百両もの配当を受けたと言っている。これは誇大であるかも知れないが、ニシン漁業の入稼漁夫の場合、二月から六月までの漁期間で、本州から入稼の平漁夫は十二両、和人地内の漁夫を使用する場合は十五両、役漁夫は二十両、船頭は二十五両というのが当時の相場で、和人地漁夫は殆ど役漁夫であった。従って漁業者の収入は、ニシン漁業の二十両、磯廻漁業と昆布、鮑等の収入五両、サケ漁業への出稼が十両、併せて三十五両前後というのが当時の漁業者の平均収入であった。 江戸時代の後期、江戸庶民の生活は、五人世帯で年十両の生活であったといわれる。それを蝦夷地と比べれば、二倍半以上の収入があったことになり、僻遠の地で物価の高さはあったと思われるが、ニシンが豊漁でありさえすれば、漁家の生活は満ち足りたものであった。 【サ ケ】 サケは「鮭」「年魚」「夷鮭」「過臘魚」「河豚」「時不知(ときしらず」「秋味」とも書く。この魚は蝦夷地で中世には第一の出産物であり、近世にはニシン漁業にその首座を奪われたが、なお漁業の双璧をなす重要な資源であった。中世の時代は塩が非常に高価なものであったので、サケの加工には用いられず、専ら内臓を抜いて一本干をした干鮭(からさけ)、または蝦夷人が乾燥を早めるため、一本干をする際皮に×印の傷を付けて製造するアタツが生産の主体であった。このサケは近世の中期以降瀬戸内海、北国地方で塩が特産物として大量 に出廻るようになると、様々な形に加工塩蔵され、本州地方に出荷されるようになった。 蝦夷地の海岸、諸河川では、多かれ少なかれどの川でも夏から秋にかけサケが遡上した。最上徳内の調査では『蝦夷草紙』のなかで、天明八年(一七八八)蝦夷地で生産された塩引鮭は四万四千石、約二万九千両としている。鮭の一石は、三〇束、一束は二〇尾であるので、この生産匹数だけでも二、六四〇万尾にも達している。蝦夷地内の生産のうちでは石狩場所がその三分の一を生産していたが、道南の諸河川でも多く獲れた。特に道南では汐止川(函館市字石崎)、茂辺地川、知内川、天の川、厚沢部川、遊楽部川、利別 川等が多く獲れ、中野川(木古内町)、福島川、及部川(松前町)、石崎川にも遡上した。 福島地方では中世どの河川でもサケが遡上したようであるが、特に福島川についてはこの時代からサケの獲れていたことが記録されている。『新羅之記録』によれば上之国城代南条越中廣継の内儀(四世季廣の長女)が陰謀を企て露顕し、斬罪に処されたが、その際、「穏内の折加内村を両人の牌所(はいしょ)、長泉寺(のちの法界寺)領と爲す。此所の川鮭魚多く入ると雖も、寺領と爲るの後鮭魚川に入らず。然るに三十三回忌過ぎて以後鮭魚川に入る事奇特と謂ひつ可きかな。」とある。この事件は永禄五年(一五六二)のことであるので、三十三年後とは文禄四年(一五九五)で、この時には福島川にサケが戻って来た、と記している。これは中世の年代にサケが多く遡上していたことを表す証拠である。 近世に入って、町内では第二の川である澗内川(字白符と宮歌との堺川)にも多く遡上していて、これを捕獲していた記録がある。『宮歌村沿革』では村の草分け時代に澗内川で曳網によってサケを二三〇束水揚げをしたと記されている。一束は二〇尾であるので、この時代澗内川で四、六〇〇尾以上のサケが捕獲されていたことが分かる。この数字から類推すると、福島川ではその三倍以上の水揚げがあったと考えられる。 遡上するサケを採捕するには、古くはマレックという棒の先に鉄の鈎(かぎ)の付いたものを用いた。この棒を河中に入れておき、サケが当るとその先の鉄の鈎が反転して、サケを押え込み水中から引き上げる方法で、主にアイヌの人達が多く利用した。和人は河中に簗 (やな)を設けて遡上を遮断し、そこに網を張り、曳網で採捕するという方法が取られていた。 近世になって塩が大量に出廻るようになると干鮭(からさけ)、アタツの一本干から、塩引鮭の製造に主力が移り、蝦夷地に出向く積取船は船腹に積めるだけの塩叺(かます)を積んで行き、現地で水揚げされ内臓を除いたサケを船倉に入れ、塩漬にして本州各地に出荷した。十月を過ぎてもサケは遡上するが、積取船は初冬で危険なため現地には行けず、そのころ水揚げしたサケは内臓除去の上、塩をして囲っておき、冬中は冷凍保存し、春一番に積取って出荷するものを冬囲(ふゆがこい)と称した。当時サケの加工品は、文化年間末の著と思われる『松前産物大概鑑(たいがいかがみ)』によれば次のとおりである。
というのがサケの加工法である。これによるとアタツ(アダツ)の製法が近世に入ると、中世とは異なる製造へと変化している。 サケと同類の魚にマス(鱒)があるが、この魚は蝦夷地海域、諸河川で獲れたが、塩の加工利用が可能になった享保期前後から塩鱒の需要が増加し、寛政、享和期(一七八九~一八〇三)ころにはマス〆粕、マス油の生産が多くなった。特に釧路、ノシャプ、国後島から北方の海域に多く、享和三年のマス〆粕の生産額四十万貫、代値は一万四、四二八両に達している。これはマス油の需給が多かったので、生マスを煮て油を精製し、さらにその段階で生ずる〆粕を乾燥した後、農業用の肥料として関西、北国方面 に売り出し、好評を得て需要が増加したものである。マスの加工品としては
である。この鮭鱒漁業が陸岸および河中でオコシ網を用いるようになったのは、文化年間からといわれている。 【コンブ】 中世以降蝦夷地を代表する海産物にコンブ(昆布)があった。中世には蝦夷地のウンガ(宇賀)の昆布は室町時代の『庭訓往来』のなかで、主要物産として位 置づけられている。その昆布は中世日本海の貿易港小浜で加工されて、若狭昆布として関西市場を独占していた。このコンブの生産地は、和人の住む地域の東端の宇賀、志濃里(志苔)であった。 近世に入るとそのコンブの生産地が拡大し、内浦湾(噴火湾)にまで広まっている。『新羅之記録』によれば、寛永十七年(一六四〇)六月十三日の項に「内浦岳(駒ヶ岳)噴火し、その勢で津浪が発生し、百余艘の昆布取の舟の人残り少なく津浪におほれ死に終る」と記されていて、この年代には後の六ヶ場所といわれる鹿部付近にまで昆布の採取地が拡大している。また、享保二年(一七一七)の『松前蝦夷記』には、「一昆布 右東郷志野利浜ト云所より東蝦夷地内浦嶽前浜まて海邊弐拾里余之所ニ而取申候、尤献上昆布ハ志野利浜宇賀ト申所之海取分能ゆへ取り申由収納」とあって、昆布場所が東に伸びる傾向にあった。さらに商場、場所請負が進展した享保年間(一七一六~三五)には太平洋岸の三ツ石、浦河、様似付近まで多くのコンブ取が進出し、また、アイヌ人の採取、加工の方法が教えられ、交易物資の仲に入るようになり生産量 は増加した。 コンブ漁は五月末から八月末まで続けられ、各村では正月の大寄合で予(あらかじ)めその予定を決めておき、鎌下しは村役で協議して日取りを決定した。したがってこの鎌下しの日より前の勝手な採取はできず、元禄五年(一六九二)の亀田奉行の定書の中にも、「一、昆布時分より早く新昆布商売候義堅命停止候」とあって、若生い昆布の濫獲を防ぐ対策がとられていた。 この生産されるコンブの質は、志濃里、宇賀地方のものは、幅広で、丈も長く赤昆布と言われたが、その理由について『松前蝦夷記』では、
とあってこの赤昆布を最高級のものとして、これを亀田地方(函館市を含む海岸地方)の採取村民からは一戸に付、切昆布二十五駄 (元揃の良い所を取ったあとの末昆布。一駄は長さ三尺のもの五十枚を一把とし四把で一駄 )の昆布取税役を課し(のち十三駄となる)、さらに献上用赤昆布五十枚を課していた。しかし、この赤昆布は、コンブのなかでは品質はよくないものであるが、色彩 的には見映えのするものであったので珍重されていたという。 昆布には多くの種類があり、津軽海峡から太平洋沿岸にかけての昆布は赤昆布、青昆布、元昆布、真昆布、三石昆布、水昆布、黒昆布等があり、また産地によって志濃里昆布、松前昆布等があり、また、結束法によって元揃昆布、長折昆布、切昆布等と言われた。太平洋沿岸の大幅、長尺の良質昆布に比べ、津軽海峡西部から日本海に生長する昆布は、丈三、四尺、身幅五寸のもので細目昆布で商品価値も少なく、主に家庭のだしコンブとして利用される事が多かった。また、このコンブを乾燥させた上臼で搗いて粉にして保存し、オシメ昆布として飢饉のときや、米価騰貴の際の飯に混ぜて食べる食料となっている。コンブの価格は上一二〇文、中一〇〇文、下八〇文程度であった。
このコンブの需要は関西が主体で、小浜や京都で加工され商品価値を高めていたが、さらにコンブの需要が伸びたのは、清国貿易用として長崎へ積出されるようになった元文五年(一七四〇)以降といわれる。また、宝暦六年(一七五五)以降には長崎産物会所が毎年手代を派遣して、松前の商人と契約し海鼠(いりこ)、白干鮑(あわび)、志濃里昆布の三品を買上げていたが、昆布以外の品が、仲々買上げ予定数量 に達せず、藩がその達成を命令するということもあった。 コンブを採るには鎌または、捻掉(ねじりざお)、二又棒(まつか)を用いた。その方法は地方によって若干差があったが、福島方面 では二又棒か、鎌を用いた。二又棒は長さ三間程度の棒の先に、二本の木のマツカを付け、柄の部分を設け、これを海中に入れて捻り廻すと、コンブがからみ付き、これを力を入れて引き抜き水揚げをする。また、鎌はマツカと同じ木の先にのこ切状の鎌を付け、海中でコンブの根を伐って静かに水揚げるもので、作業的にはマツカの方が有利であったと言われるが、この生産量 を示す史料は残されていない。 【イカ釣漁業】 イカは「烏賊魚」あるいは「柔魚」と書き、製造して乾燥されたものを鯣(するめ)と呼んだ。この鯣は昆布、勝栗と共に武将の出陣の縁起物となったり、貴族の酒席のつまみとして珍重された。近世初期にはイカ釣漁業は日本海、特に佐渡島より以南の地で発達していた。 蝦夷地では往古から近海に多く棲息していたが、これを釣る技術が分からず、これを本格的に漁獲することが出来なかった。松前廣長筆の『松前志』は天明元年(一七八一)刊行されたが、この中では「近年海人捕り得ることを得たり」としているので、この時代前後に漁獲方法を知り、この釣漁業が始まったものと考えられ、この技術は恐らく佐渡島から伝承したものと考えられる。しかし、漁業として成り立つ程の本格的漁業ではなかったと思われる。
津軽弘前の郷士平尾魯遷が安政四年(一八五七)松前に着いて、箱館へ向かう途中の村々を描いた『箱館紀行』の絵を見ると礼髭村の部のなかで、婦人が海岸の納屋にイカを干し鯣を製造している場面 が描かれているところから、この年代頃にはイカ釣漁業と鯣の生産が本格化してきたことが考えられる。 明治初期の一ノ瀬長春筆『北海道漁業図譜』に吉岡村のイカ釣用具が描かれているが、その中にヤマテの絵があり、この天秤は鯨骨を用い、その下に二五〇匁の鉛を結び付け、その両側に餌を付けた釣針が仕掛けている。 また箱館、上磯、熊石、久遠方面ではこのヤマテの針は、針四分程のものを上向並列し、上部にイカを巻き付けた針を二組下げており、瀬棚方面 では一尺の桐の木台の先に二本の竹を結び、その先に針を下げたものなど、その地域によって漁獲方法も様々に摸索していた時代であった。 この鯣の製造は、幕末箱館が開港され、長崎を介さない蝦夷地生産物を直接売捌(さばき)する箱館産物会所ができ、清国貿易の俵物類が箱館から積出すようになると、それまであまり着目されなかった鯣の需要が急に伸び松前藩は安政四年(一八五七)領内に「領内出産鯣は時相場を以て買上るに付き密売買を爲すべからず。漁業者出産物を引当に前金借入を出願する者は、会所より米穀又は金員を貸与すべし。且つ商売等鯣入用の者会所に出願するに於ては払下を爲すべき」旨を告示している。これは松前藩の収荷を一元的にその手に収めようと画策していたものと思われ、安政六年以降箱館産物会所の鯣取扱量 は、同年一五万八、五四七斤(二万五、三六七貫余)であったが、三年後の文久三年(一八六三)には、鯣取扱量 は三〇万五、二四六斤と量は倍以上に伸びている。 イカ釣の漁法は、磯舟または保津船で夕時出漁し、陸岸近い海でかがり火を焚いてイカを集め、それをヤマデ(山手)、またはハネゴで釣る。ヤマデは八尋ないし一〇尋位 の深い海中のイカを釣る際に用い、ハネゴは一尋か二尋というごく浅い海に浮き上ったイカを釣る際に用いたが、この方法は昭和前期にまで継続されている。 【アワビ突き、イリコ曳漁業】 アワビは「石決明」「鮑」と書き、イリコは海鼠(なまこ)、この煮干ししたものを海鼠という。松前地方の磯廻り漁業としてはコンブ、ワカメ、雜魚釣と併せ重要な漁業であった。 アワビは古くは串貝に製して本州に移出され、松前藩の幕府献上物のなかには、干鮑、串貝の名が見られる。このアワビの産地は『北海道漁業志稿』では、その中心が松前地で、主産地として松前礼髭、宮の歌、福島、小谷石、知前(内か)、函館等の名が挙げられ、その他では久遠、太田、太櫓、瀬棚付近、積丹半島、厚田、浜益、留萌、天売、礼文島などが挙げられている。 文久二年(一八六二)箱館産物会所清国輸出用アワビの目録を見ると
となっていて礼髭村から小谷石村の生産量が、アワビ生産上極めて重要な地位 を占めていたことが分かる。 福島地方のアワビ突きは春期および夏期の比較的穏やかな日に、磯舟にアワビ突きの扠(やす)を積んで、一尋か二尋の比較的浅い磯廻りで漁をする。扠は長さ三間位 の木の棹の先に、鉄で先の尖(とが)った釘を三本付けたもので、これを使って水中のアワビを殻を壊さないように挾んで引き上げる。アワビを採るためには水中を捜すが、近世初頭ではガラス箱とてなく、漁師は海中に顔を突っ込み、水に目を慣(な)らして扠を使ったが、幕末に到って外国産の板硝子(ガラス)が輸入されるようになると、これを利用したガラス箱が出廻るようになり、高価ではあったが生産量 は増加した。 アワビは生のまま食料にしたほか、加工されて本州へ移出したり、長崎俵物として出荷した。最も古い加工法は串貝で、丸竹の串でアワビ五個を貫き天日で乾燥し、十串をもって一連とし、目方は約五〇〇匁であった。正徳期(一七一一~一五)ころからこのアワビが長崎俵物として出荷されるようになると、清国の需要に従って白干鮑が生産された。この白干鮑は生アワビを蒸し、又は煮て塩をふり、ねせてから乾上げたもので、このほか黒干鮑もあった。黒干しはアワビを煮て塩をふらず天日で干したもので、全体に黒く仕上るので、値段も安かった。このほかに〆貝と称して生アワビを塩漬にし、二斗樽に五〇〇個入れたものもあった。 当時はこのアワビの生息も多く、当地方の磯廻漁業のなかでは、コンブに次ぐ収入があり、ニシン漁からサケ漁までのつなぎの漁業として重視されていた。 イリコは海鼠と書いたが、方言ではナマコと呼ばれていた。海鼠(いりこ)とはこのナマコを煮て乾燥させたものである。このナマコは蝦夷地では釧路、十勝地方を除く全域に生息し、特に寒冷地帯の沿岸に多く産出された。古くから食料に供され、本州へは乾燥して移出した。寛文七年(一六六七)の記録には、敦賀への送り荷物のなかにイリコの名が見え、松前藩の藩法である『松前福山諸掟』に海鼠曳奉行の役職について示している。それによると、
とある。年代は不明であるが、和人地の漁業者が、蝦夷地のイリコ曳に船で出稼していたことが伺われる。 イリコを曳(ひ)くというのは鉄で枠を造り、その前部に入口を設け、下部には鉄の爪(つめ)を付け枠の後方には八尺という網の袋を付けたものを磯舟で曳き、海中のイリコを獲るというもので、蝦夷地では一日一艘平均四〇〇個のイリコを獲り、多いときは二、〇〇〇個に達したという。和人地での主要産地として、礼髭村から福島村が最も良い漁場とされていた。 この水揚げしたイリコは内臓を取り、丸煮したものを一〇個ずつ串に貫き、炉上に吊し、又は日光で乾燥して串を抜き、バラにして俵に詰め、俵物として出荷した。 享保年間(一七一六~三五)ころから長崎俵物の中心として、アワビと共に清国に送られた。アワビ、イリコは全国生産の約七割を占めたので、長崎会所は入荷の促進を図るため、毎年手代に金を持たせて松前に派遣し、松前で一手に買付けする近江商人の団体両浜組合と協議して、その年の出荷予定量 、予定価格を定め、契約をして手付金を手交する。これには藩も立会して、公正を期した。この元請人達は、各村を廻り村役と協議し、予定量 を定めて手付金を交付した。この手付金は冬期間に交付するので、冬期で収入のない漁業者は大いに生活が助かった。したがって、割当量 の出荷が完了するまでは、長崎俵物以外の横流しは許されなかった。 【イワシ】 イワシは「鰯」「海鰮」とも書き、蝦夷地では秋九月、十月に津軽海峡の東口から西に向かって北上し、主に恵山岬から汐首岬が中心漁場であった。蝦夷地ではニシン漁が中心であったので、この漁に重きを置かなかった。我が国のイワシの中心漁場は九州の国東(くにさき)半島、関東の九十九里浜で、ここでは干鰯(ほしか)を製造して全国田畑の金肥として供給していたが、両漁場の資源減少によって、蝦夷地の胴鯡 (どうにしん)、白子、笹目等が、享保年間(一七一六~三五)ころからその代替として急激に需要が増加したものである。 この時代蝦夷地では生で食べるか、丸干ししたり、塩漬にしたり、糠漬にするより方法がなかった。福島村では月の岬から塩釜(釜谷)付近がこのイワシの好漁場であった。しかし、この貯蔵のためには塩を必要とした。そこでこの塩釜地区で製塩をし、塩釜の地名が生れたものである。常磐井家文書の『福島沿革』では、 とあって、この年代の少し前から製塩の始められていたことが分かる。
また、イワシ網の操業について『戸門治兵衛旧事記』には、
とあって字月崎と字塩釜間の赤川でイワシ網漁が行われていたことが分かる。また、明治元年十月末の箱館戦争の際、知内村萩砂里(はぎちゃり)に夜営していた徳川脱走軍に夜襲をかけた際、福島村に出陣した松前藩兵のうち、渡邊々(ひひ)を隊長とする約五〇名が、二艘の鰯枠船で出撃したことが記録されている。これらを見ると幕末には福島村で、秋に本格的にイワシ漁が行われていたことが分かる。 【クジラ】 クジラは「鯨」と書き、また「海鰌」「勇魚」とも書く。古くは「イサナ」「オキナ」「カミ」「エビス」とも呼び、蝦夷人は「フンベ」と称した。このクジラは蝦夷地近海には大クジラは居らず、長さ拾丈(三〇メ-トル余)が限度としていたことが『松前志』に記されている。この蝦夷地近海を廻游するクジラは、沖合の魚を陸岸に追上げるといわれ、漁業者にとっては幸福をもたらすことからカミ、エビスと呼ばれた。 このように呼ばれる理由には、もう一つの訳があった。蝦夷地近海は多くのクジラが居ながら、これを捕獲する技術を知らなかったので、廻游に任せるのみであったが、たまには弱ったクジラが寄(よ)り鯨(くじら)として海岸に打ち上げられることがあった。寄り鯨があった場合は、藩法に従い発見した村の村役から藩に届け出、藩の役人の検分を受けて、その村が所有権を確定し、村内で解体して配分するが、その際は近隣の村にも多少配分することが義務付けられていた。 『戸門治兵衞信春旧事記』(常磐井家文書)によれば、
この記録では、当時福島村の枝村であった小谷石村と知内村の村境であった赤石浜に寄り鯨があり、この発見を福島村と知内村から藩に報告したが、その領有権をめぐって紛争があった。そこで立会見分として足軽武川七右衞 門という者が来て、蛇の鼻岬をもって両村の村境とした。さらに陸通りも調べ、陸の村堺は知内川と温泉の川の合流点である栗の木椹(たい)坂(さわらの木のある坂)が、両村の境界となったといわれ、したがってこの寄り鯨の所有権は小谷石村のものとなったが、知内村支村の脇本村にも若干の分配があったと思われる。一度寄り鯨があると、村中で解体し分配する。クジラは肉も油も塩蔵して冬期間の食料にしたり、内臓や油を煮て鯨油(げいゆ)を採って、灯明の油にする。さらに肉は焼いた石の上にあげて熱を通 し、石焼鯨を製造して保存した。このように寄り鯨があると村内の人達は、一月(ひとつき)も二月(ふたつき)も恩恵を受けるので、住民に幸いを与えてくれる神様としてエビス様の尊称で、尊ばれてきたものである。 【サ メ】 サメは「鮫」と書き、または「鱶(ふか)」「ワニザメ」と称した。この魚は近海によく廻游したが、当地方の 人達はあまり漁獵しなかった。しかし、この魚が沖合に廻游すると付近の魚がみな恐れて陸岸に近づいてくる。したがって沖にサメが居ると陸岸では大漁するという言い伝えがあって、神としてあがめられていた。今は猿田毘古神を祭神とする松浦の白神神社(楚湖神社ともいう)は、古くはこのサメを祀る祖鮫(そごう)明神が御神体であった。 秋田の文学者であり博物学者であった菅江真澄の旅行記『えぞのてぶり』で、吉岡山道を通 過する際の記録のなかで、
とサメの事を記している。 このほか蝦夷地の北方には多くのチョウザメがいた。このサメの皮は菊形、蝶形の模様があって、これを刀の鞘(さや)の飾りに用い珍重した。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||