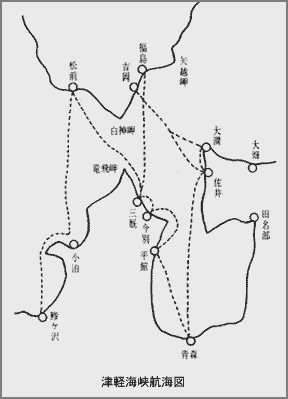|
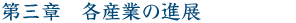 |
| 第五節 海上交通 |
全面に海を控え、本州北端地方と対峙する福島町にとって、本州との船をもっての海上交通 は、極めて重要なものであった。遠くは文治五年(一一八九)藤原泰衡の残党が蝦夷地に渡海する際は、三厩(東津軽郡)から船に薙刀(なぎなた)を結び艪櫂(ろかい)として、吉岡村へ漕ぎ渡ったといわれる。しかし、本州最北端の龍飛岬から本道最南端の白神岬まで二十二キロメ-トルの間は、龍飛・白神・中の潮といわれる最も激しい潮流が流れており、航海上危険が多く、犠牲者も多かったので、近世初頭においてはこのル-トを避け、比較的に潮の流れの弱い日本海側の小泊(北津軽郡)と松前を結ぶ線か、海峡中央部を佐井(下北郡)から箱館に向うル-トが多く利用されていた。
徳川幕府が将軍代替の際派遣する巡見使の行程を見ても、第一回の寛永十年(一六三三)の分部左京らの一行は、北津軽の小泊から松前に入国し、同じコ-スで津軽に渡っている。また、元和元年(一六一五)第七世藩主公(きん)廣参勤交代出途の際も松前から小泊を経て、高岡(現弘前市)に至っている。これらは白神、龍飛間の危険な海峡を避けて往行していたものである。しかし、安全だと思われる地域の航海にしても、良風を経なければ渡海ができなかった。一六一八年(元和四)のアンジェリス神父の『第一回蝦夷国報告書』で、恐らく鯵(あじ)が沢と思われる港を出たところ逆風のため深浦(西津軽郡)に入港し、ここで二十二日も風待ちをした上で出帆したが、嵐に遭い松前には着けず、ツガ(テンガ-、天の川)という港に着いたが、僚(りょう)船は瀬棚まで流されている。このように海峡を横断するということは、経験豊かな水主をしても、容易なことではなかった。
寛文年間(一六六一~七二)ころになるとようやく津軽半島の東側の港三厩と松前との間の海上交通 の記録が現われる。寛文二年に津軽産米を青森から積み出し、松前に移送したとする記録があり、当然この海峡を横断したことが考えられる。さらに寛文九年(一六六九)の日高地方の騒乱の際、松前藩応援の津軽藩士の筆になる『津軽一統志 巻第十』によれば、
| 松前への海上船道積 |
一青森より
一内真部(青森市)より
一蟹田より
一平館より
一三馬屋より
一深浦より
一鯵ケ澤より
一小泊より |
二十二里
二十里
十七里
十四里半
九里
二十五里
十八里
八里 |
一油川より
一田より
一野内より
一今別より
一うてつより
一金井澤(が)より
一十三より |
二十一里
十八里半
十五里
十里
七里
十八里半
十一里 |
とあるので、この寛文年間には、これらの港と蝦夷地の間の海上交通 が行われていたと思われる。しかもその海路の拠点となるところは東津軽郡地方が多いのは、この地方が近世初頭より利用されていたことも考えられる。『新羅之記録』によれば、「永禄三年(一五六〇)春慶広朝臣(松前氏第五世)十三歳にて津軽に渡り波岡の御所右衞 門督顕慶(すけあきよし)朝臣(あそん)に謁す。此時松前より渡海船着のため、稲我郡潮潟の野田玉 川村を賜わる」とある。野田は現在の東津軽郡平館村に字野田の地名があるので、蠣崎慶広(のち松前)が本州へ渡る場合の船着場として、波(浪)岡城主北畠顕慶朝臣から拝領したとされている。その後顕慶が津軽爲信に討ち滅されているので、この船着場は利用されなかったと思われる。
松前氏の三厩まで海行し、ここから青森を経て陸奥街道または東北道と呼ばれる街道を通 り、江戸へ参勤交代するル-トの初見は、『青森沿革史』によれば、延宝四年(一六七六)九月松前若狭守(矩広の私称か)は、平館を発足、当御所御着、御定宿大坂屋与兵衞 方に御入り遊ばさるとしていて、この時点では平館を松前からの渡航先としている。
しかし、十七年を経た元禄五年(一六九二)の『松前主水広時日記』では、松前渡海の拠点を三厩に移している。同日記によれば、江戸参勤出仕中の松前家第十世藩主矩広が、元禄五年二月九日出立帰国の途につき、三月四日松前到着までを詳細に記しているが、この行路は二十六日間に及ぶ長いものである。この間の青森から松前間の旅行を摘記すると、
廿七日
(野辺地)暁七ツ時(午前四時)御発。
小湊御昼、夕七ツ時(午後四時)過青森御着御泊り。津軽越中守様より御使者。
廿八日
暁七ツ時御発駕。蟹田御昼、夕七ツ時平館御着泊り。松前より御迎として太田六郎兵衞 参り御目見。
廿九日
暁六ツ時(午前六時)御発駕。今別御通りに小鹿喜右衞門宅へ御立寄御馳走有之被下被遊。御道中天気能、夕七ツ時過三馬屋へ御着。
三月朔日
風下り、御風待。
同二日
西風、同
同三日
同合風、同
同四日
東風天気能御船中万端無二御別条一、昼四ツ時過松前へ御安着、御社仏参。
同五日
御家中一同御礼被爲(おうけな)二御請(されらる)一。 |
とあって、元禄年間より三厩(三馬屋)が松前氏の着船基地となっていたものと考えられる。しかし、同記録中には、三月十五日江戸への使者として出帆した蠣崎蔵人(くろうど)は平館まで直航し、その際の船賃(借上料)は小判二十七両二分であったとあるので、三厩、平館が混用されていたものと考えられる。
三厩-松前間の藩主参勤コ-スとしての航路が確定されてくると、航海の安全を計るため、白神岬と龍飛岬に狼煙(のろし)台が設けられた。寛政二年(一七九〇)最上徳内筆の『蝦夷草紙 巻之一』には、
狼煙(のろし)の事
一、松前の領主東都へ参勤の時、松前と津軽の灘を渡海の節、定例にて長者丸、貞松丸、〔別 本貞祥丸に作る〕といふ手船二艘にて、松前の泊を開帆して津軽三馬屋の泊に渡り至る。海上無事に着岸すれば、津軽領の宇鐵村清八といふ獵師の定役として狼烟をあげ、海上無事に着岸ありたる其しるしを、松前へ告知らしむるあひづなり。松前の白上〔別 本に白神に作る〕にて此の狼煙を見て、主人つゝがなく三馬屋に着岸ありたるを知て、白上にても相図の篝(かがり)をたく。此かゞりを見て、松前城中にても又篝をたく也。宇鐵、白上、城中と三ヶ所の火を通 して後宇鐵の火の消るを見て、白上と城中ともに皆火を消すなり。此狼烟は松前と津軽と隣国の好みによって也。津軽の領主にてもかねて用意ある事也。松前領主よりは獵師清八に青差二貫文褒美として給はる也。
(北門叢書第三冊による)
|
とあって、松前城中と白神岬、対岸龍飛岬の三か所に狼煙台があり、特に津軽の領地内である龍飛岬の狼煙台は、三厩村の枝村宇鉄の清八に対し、松前藩が手当を与えて管理させていた。
松前藩主の参勤の場合、日程が決まると藩主は菩提寺法幢寺、八幡社、神明社に巡拝して、参勤留守中の領内安穏と、行旅の安全を祈る。さらに日を定めて侍中、神官、僧侶、町年寄、村方名主、御用達等の挨拶を受けたのち、日和(ひより)待ちに入る。各神社では海上安全、道中安全、御日待のお神楽を斉行して、出帆のできる良風が吹くのを祈る。松前を出帆するには北、北西、西の風で津軽地方に向けて船出し、同地方から松前に向かう場合は、東、南東、南の風が良いとされていた。
渡海日和となると侍中に出発時刻が知らされ、御目見得以上の者は馬出口から沖之口役所前に並んで藩主を見送り、沖合の本船までの間は橋船で連絡し、乘船が終った本船は、数十艘の曳船で潮路にまで曳き、開帆して三厩に向かう。三厩に安着し狼煙が揚がると、白神がこれを受け、城中に知らせる。城中はこれを受けると太鼓櫓の太鼓が鳴り響き、諸侍中は裃で盛装して登城の上、大広間で留守居の家老に「御無事の御渡海、執着(しゅうちゃく)に存じます」と挨拶をするのが慣例となっていた。
一方、三厩から松前への航海は、天明八年(一七八八)七月巡見使藤沢要人、川口久助、三枝(さえぐさ)十兵衞 の一行に随従した地理学者古河古松軒正辰が、この巡見で見聞したことを記録した『東遊雜記』に詳しいので、その詳細を知るため、次に引用する。
七月十九日天気悪しく、松前渡海ならずして、三厩に滞留。宿主越後谷権十郎、この所を三馬屋と称せし伝説を云ふ。…略…
三馬屋浦にて浦人を招き、松前渡海の里数を尋ね聞きしに、みなみな海上七里という。予遠見せしに信じ難く、この辺の土人は陸地の行程をも知らぬ ことなれば、猶更に知れ難く思い、夫れより松前の地へ度々渡海せる船頭をたづねて、其の家に至りて聞きしに、一定ならず、又津軽侯より御馳走に出し給う御船頭に対面 して尋しに、我らは鯵ケ沢居住の者にて、この度渡海は始めてのことにて詳しくは存せずという。鯵ヶ沢という所は、弘前より西に当る所にて三馬屋より三十里もへだてし浦なり。
御巡見使御下向について、御船頭役にこの地へ御召しにて始終夢中の人々なり。予もおかしく詮方なく思いし所に、町はずれに手習師匠せし若者に佐兵衞 という人あり、この者万事に才ある由聞き出して、其の尋ね行きて海辺の地理を尋ね見しに、所相応の才子たりしゆえ、大いに嬉しく、海上汐の行事まで委しく聞きしことなり。
三馬屋より龍浜鼻まで三十六町、道にて三里近し。龍浜鼻より白神まで七里、しかし松前の津までは十里に少し遠し。右の如く僅かなる海上といへども、西の方数千里の大海より東海へ行く汐片潮にて、其の急なること滝の水の如し。海上に三つの難所あり。所謂(いわゆる)、龍浜の汐、中の汐、白神の汐と称し、龍浜の汐というは、汐の流れ龍浜の鼻の岩石に行きあたり、そのはねさき至って強く、汐行き一段高し。中の汐というは、龍浜鼻よりはけ出し、汐さきと白神鼻よりはけ出し、汐さきと中にて戦う故に、逆波たち上りて時として定かならず。
(三一書房刊『日本庶民生活史料集成第三巻』による)
この汐行き、汐くるい不案内にて、一棹誤る時は、船を汐におし廻され忽ち危きに至ることにて、日本第一の瀬戸なり。南より北方に渡り海上長く南風にて渡り難し。その故、汐行き早き所にて船を東へ押し流し、松前の津へ入れ難し。数里の海辺みなみな石磯にて船を寄すべき所なし。箱館の浦へ志すのみなり。
夫れ故に東風の強き時は、船のほさきを小島の方へさし向け、汐に逆らいて西へ西へと乘り抜いて、松前の津に入ることにてたやすからぬ 渡海ながら、この度などは御領主より御念入り玉いて、功者の舟人数十人乘船申すことにて候得ば、少しも気づかいなき事と、しばらく物語りして宿所に帰りし事なり。
七月二十日、未明より順風に候まま、御船へ召され候へと、津軽の役人中より案内ありし故に、御三所の上下取り急ぎ、五つ頃乘船す。津軽侯より古例にまかされ、百石積み位 の館舟数艘にて紫の絹幕引き廻し、鳥毛の長柄十本吹貫(のぼり)一本(是れは黒白赤の目印にて、引舟に合印の籏立ててあり)引舟は本船一艘に三十艘宛。供船三艘、津軽侯御馳走の役の舟三艘、何れも幕をかけ、彼れ是れ百艘ばかりの舟数故に海上賑々敷く、上の御威光の厚きに感じぬ 。
夫より津軽侯の役人より船玉へ御酒を捧げ、船歌を奏すれば、水主、揖取同音にうたう。定めてならしなどもせし事にや。声を揃いて面 白き音声なり。後に聞けば黄帝という舟歌なり。右祝言終れば御本使の船を始め、太鼓をたたき立て、引舟合印の目印に合せて、我れ一番に漕ぎ出さんと引綱を本船に投げかけ、大勢曳々(えいえい)と声を揚げて漕ぎ出す体、陸の案内者とは引替り海上なれし漁士どもなれば、中々いさぎよく、船軍抔(ふないくさ)もかくあらんと大いに面 白く、各々興に入りし事なり。
程なく龍浜近かくに至ると、船を止め、鳥毛を始め幕に至るまで取り納め、板を以って船を包み廻し、揖穴までも汐入の処に苫を立て、船頭より申し上ぐるには、是より海上荒く候まま御用心のため、恐れながら是に差し置き候とて、板にて結びし小さなる桶を数々取り出せしなり。何にせる事にやと心を付けて見れば、船に酔うて吐逆せる時の用心桶なり。各々これを見て気味悪しく思いし事なり。夫より水主二人、海草にて製したるを頭よりかぶる蓑(みの)を着し、艫に出て環に綱を通 して己が腰に高々と引きまとい、汐越波になで落されぬ用心なり。
揖取四人、右の装束にて揖つかの左右に並び、各々の環に同じく綱を以って其の身をくくり付ける事なり。龍浜鼻にかかると引舟はちりちりばらばらとなりて、元の三馬屋へ漕ぎ帰る事にて、船頭の太鼓の拍子につれて夫より帆を揚げ、龍浜鼻の汐を乘り出すと艫の水主声を揃えて『只今龍浜の汐にかかりし』と高声に揖取りに知らす。(同音に声を揚げざれば波音高く揖取りの処へ聞えず)取揖、おも楫も隙なく知らせ、船行き、汐の調子にかなえば『ソロウタ引け』と呼ばわる。
荒波立上りて船の上を打越す時は、水主、揖取り、同音にて『船玉明神たのむぞたのむぞ』と声を揚げて太鼓を打て拍子に乘じて船をつかう事なり。
この日三枝侯の召されし船、仕合せよくていづれの汐も程よく乘り切り、一番に松前国に入れば、又々元の如く船かざり急がしくことたる事にて、松前の津には引舟数十艘、合図の籏をひらめかし御迎えに出るより、御三所の船には船頭初めの如く同音にうたいつれて、鼓をならし櫓拍子高くこぎ入れば、引き舟来たりて綱繁く入るよそほい筆紙に尽くし難し。
陸には松前侯の諸士列を揃えてお迎えに出向かう。海上より城郭を見れば、楼造りにして遠見いわん方なく、市中軒をならべ、かかるよきところとは、人々夢にも知らざりしと目を驚かせしことなり。この渡海のことを追々委しく聞しに、昔より難船の沙汰なし、至って難海故随分と日和を見定めて、少しにても心にかかる天気なれば、決して渡海せざる故という。尤もの事にして万事にこの心ありたきものなり。…略 |
このように、津軽海峡を本州北端から蝦夷地に向って乗り切ることは、この海峡を熟知している船頭、水主でも容易なものではなく、従って万般 の準備と、十分の天候調査をした上でなければ出帆はしなかった。龍飛岬に差しかかると神仏の加護を願いながら必死に操船を続けて、松前の港に入った。
松前藩は当初長者丸、貞祥丸の二艘の手船を所有していたが、文化四年(一八〇七)の移封の際これを商人の委託に任せた。その後天保年間(一八三〇~四三)の『近江藩蝦夷記録』によれば、松前藩の手船は、
| 吉祥丸 |
六百三十一石 |
船頭惣兵衞
宿阿部屋利兵衞 |
| 長者丸 |
九百十三石 |
船頭百造
宿大津屋武左衞門 |
| 叶 丸 |
九百三十一石 |
船頭喜四郎
宿種田屋治左衞門 |
| 天神丸 |
|
|
の四艘で、これら手船は総て商人に委託し藩主が参勤交代の際や巡見使の来島等の公用にのみ使用し、それ以外は商人の運用に任せていた。
このような約千石の大船は狭い海域で、激しい風と浪では操船は容易ではなく、遭難の可能性も高いので、あまり用いず、小形の百石から二百石の船が主に用いられた。これらの船は中漕船(なかこぎせん)、中遣船(なかやりせん)、押切船、小廻船、早船と称する天当(てんとう)船等が主体となって海峡を運行していた。このように海峡の航行が頻繁になると海難事故も増加する。さきの『東遊雜記』では、この海峡横断は万全を期しているので遭難は少ないとしているが、この海峡を乗り切れず、吉岡や福島に多くの船が漂着したり、破船する船も多かった。
松前から三厩、平館へと航路が定形化すると、この航路はさらに青森港に延長するようになり、蝦夷地向けの生鮮食糧品や野菜等の供給港となり、一方は佐井、大澗を通 して箱館との交流が盛んになるが、危険も増大してきている。次の史料を見ても松前から出帆した買積船が三厩から平館を経て、青森に入港したのは二日後で、荷積や風待ちで十日間を経ている。さらに青森を出帆して龍飛岬を経て松前に向ったが、海峡を乗り切れず、吉岡、福島方面 に落船し、南西の風を避けるため矢越岬を越えて、知内村枝村の脇本(現在の同町涌元)に避難し、ついには漂流して札苅村コウレン崎で破船をしているが、その間の日数は二十二日も要している。
直乘船頭
水主馬形町
水主佐渡扇田ノ
同津軽小泊ノ
以上 四人
右申口
|
惣吉
寅三十五才
長助
寅三十三才
勇吉
三十三才
寅吉
子廿五才 |
当月十八日朝五ツ時頃札苅村附コウレン崎ニおゐて破船仕候ニ付御村方御届奉申上候処御見分として被成御越始末逸々御糺ニ御座候。
此段私共儀年来船乘渡世罷在候処、此度津軽表江相越米買調申度、右之段御城下沖ノ口御役所江御願申上、十月九日御切手頂戴仕候処風筋不長々滞船罷在、十月廿七日亥子風ニ而御城下出帆仕候処、津軽平館沖ニ而午未風ニ爲替、廿八日平館ニ而滞船翌廿九日亥子風ニ而青森江入候所、同所ニ而餅米弐斗入百叺、白米四斗入四拾俵、味噌拾五樽、にんじん牛房六拾箇、玉 子七千積入十一月九日迄日和待滞船罷在候処、同日朝五ツ時午ノ風ニ而青森出帆、同日夕六ツ時三厩江着船。翌十日亥風ニ而同所出帆仕候処タツヒ沖ニ而未申風ニ爲替烈風ニ相成候ニ付、漸々脇本迄相越滞船仕候處、打続大時化浪高ニ而、十一月十日同十七日迄無止事烈風浪高故昼夜無油断改相凌繋留罷在候処、十七日夜ニ入弥増大時化繋留候儀も相成兼無拠(よんどころなく)浪風ニ任せ子丑ノ風ニ而御城下江向ケはしり居候処、次第烈風吹募り同夜四ツ時過ニ相成南風ニ爲吹替、致方無之猶又風ニ任せ箱館江相向居候処、大雪ニ相成地山相見得不申、弥増大浪風故船も危、手当ニ任せ上荷物投当別 迄相越申度種々相働候得共、近寄候儀相成兼、彼是仕候内札苅村コウレン崎江吹付られ手出しも相成不申浪風ニもまれ罷在候内、明方ニ相成濱辺を見候処、御人足大勢声掛ケいたし呉候ニ付、大ニ力を得相働居候内大浪風ニ而コウレン崎江打揚ケられ、船底大ニ痛水船ニ相成候事故 …以下略 前書之通聊(いささか)相違不申上候 |
| 寅十一月廿日 |
水主
〃
〃
船頭
札苅村問屋 |
勇吉 爪印
定吉 〃
長助 〃
惣吉 〃
五左衞門 印 |
| 当別御改所
伊藤源兵衞殿
|
|
| (『松前浦証文並海難聞取書』市立函館図書館蔵) |
寅年は安政元年(一八五四)と考えられるから、この記録によって、海峡横断の風行とそれによる船の運行方法、さらにはこれらの船の積荷状況、また青森から松前への航海途上での風行の変化と、落船して札苅村で遭難するまでの過程が手に取るように、かいま見ることができる。
このように帆船が松前の港に入れず、落船(風に押されて目的地に着けず他の港に着いた船)の事故が多くなる。しかし、その港には沖ノ口役所がないため入国手続や積下しができないため、松前・江差・箱館の三湊のほかにも沖ノ口役所を設けるべきだという考えが時代が下るに従って強まってきた。とくに吉岡貝取澗、宮歌澗には避難する船が多く、そのため吉岡村に沖ノ口役所(船改所)設置の必要性が、年と共に強まった。